むし歯は、感染症の一種ではありますが、風邪や感染性胃腸炎などとは異なり、自然治癒することはありません。進行の速さには個人差があり、進行度によっては一見すると治ったようにも感じることから、放置してしまう方も少なくありません。
この記事では、むし歯を放置することで引き起こされる症状やリスクを解説します。むし歯を放置していて不安に感じている方は参考にしてください。
むし歯の進行段階とは
むし歯がどのように進行していくのか確認しておきましょう。
- むし歯がたどる経過を教えてください
- むし歯の進行段階は、CO、C1、C2、C3、C4の5つにわけられ、以下のような経過をたどります。
◎CO:初期のむし歯(痛みなし)
発生して間もない初期のむし歯を、CO(Caris Observation)といいます。日本語では要観察歯と呼ばれるもので、歯の表面に穴は開いておらず、白いシミだけが症状として現れます。このシミは、歯の内部で歯質が溶ける脱灰現象が起こっている証拠で、放置していると穴が開きます。
◎C1:エナメル質のむし歯(歯がしみることがある)
歯の表面に浅い穴がある状態で、むし歯の範囲はエナメル質内にとどまります。エナメル質には神経が分布しておらず、ズキズキというむし歯の痛みを感じることはありませんが、たまに冷たいものがしみる場合があります。
◎C2:象牙質のむし歯(頻繁に歯がしみる)
歯の表面の象牙質まで達する穴が開いた状態で、冷たいものや熱いものがしみるようになります。象牙質の奥深くに歯の神経の一部が分布しているためです。
◎C3:神経まで達したむし歯(慢性的な歯痛)
象牙質を越えて、歯の神経と血管で構成される歯髄まで感染が広がった状態がC3です。安静時にもズキズキという自発痛が生じます。食事の際には冷たいもの、熱いもの、甘いもの、辛いものなど、刺激の強いもので歯痛が誘発されるようになります。むし歯の経過のなかでは、この時期がもっとも症状が強く、辛い時期といえるでしょう。
◎C4:歯冠が崩壊したむし歯(痛みが消える)
歯の頭の部分である歯冠がボロボロになり、歯根だけになった段階をC4といいます。専門的には残根状態と呼ばれ、歯髄の細胞は死滅しています。そのため、むし歯に伴う痛みは消失することから、自然に治ったと誤解される方もいますが病巣は依然として存在し続けている状態です。
- むし歯は自然に治ることはありますか?
- むし歯が自然治癒することはありません。歯の表面や根管内に感染した細菌を適切に排除するシステムが備わっていないためです。痛みを感じにくいC4の状態も、単に痛みを感じる神経が死滅しただけで、むし歯菌は活動を継続しています。
- 痛みがなくなれば治ったということではないのですか?
- むし歯は、痛みがなくなったことが治癒を意味するわけではありません。むし歯の経過のなかで歯痛が消失した場合は、痛みを感じる神経が損傷した可能性が高いです。専門的には歯髄の失活と呼ばれる現象で、ここからもむし歯は進行していきます。
むし歯を放置することで起こるリスク
 むし歯を治療せずに放置すると、どのようなリスクや症状、全身の健康への悪影響が生じるのかについて解説します。
むし歯を治療せずに放置すると、どのようなリスクや症状、全身の健康への悪影響が生じるのかについて解説します。
- むし歯を放置するとどのようなリスクがありますか?
- むし歯は、自然治癒しない病気であるため、放置すると以下のようなリスクが生じます。
◎むし歯が進行する
むし歯を放置していると、CO、C1、C2、C3、C4という段階をたどりながら進行していきます。
◎歯髄が壊死してしまう
歯髄は痛みを感じ取るだけでなく、歯に対して栄養素や酸素、免疫細胞を供給する役割も担っています。歯髄が壊死すると歯の寿命そのものを縮めかねません。むし歯を放置していると、単に歯髄が壊死するだけでなく、細菌感染によって組織が腐敗する壊疽を招き、悪臭を放つようになることにも注意が必要です。
◎歯そのものを失う
重症化したむし歯は、歯の保存することが難しくなります。失った歯はブリッジや入れ歯、インプラントといった補綴装置で補わなければならず、むし歯を治療するよりも経済的、身体的、精神的負担がかかってしまいます。
◎周りの歯にむし歯がうつる
むし歯は細菌感染症なので、放置していると感染の範囲が広がります。むし歯の両隣りの歯は、むし歯がうつるリスクが高いため注意が必要です。
◎根っこの先に病巣ができる
放置したむし歯には、根っこの先に病巣ができる根尖性歯周炎がよく見られます。
◎歯性感染症を誘発する
むし歯による細菌感染は、周囲の組織にまで広がることがあります。その結果、生じる歯槽骨炎、顎骨骨膜炎、顎骨骨髄炎、上顎洞炎、蜂窩織炎などを歯性感染症といいます。
- むし歯を放置したときに現れる症状を教えてください
- 放置したむし歯がC4まで進行すると、ズキズキとした歯痛は消失しますが、噛んだときに痛みを感じる咬合痛が生じる場合があります。根尖性歯周炎に伴う症状のひとつです。根尖性歯周炎では、歯茎が赤く腫れて、膿が出てきたり、歯が浮いたような感覚を覚えたりすることもあります。
歯茎だけでなく、顎全体や首にかけて腫れが認められる場合は、歯性感染症が疑われます。歯性感染症を発症すると、患部に強い痛みが生じたり、発熱や倦怠感を伴ったりすることもあるでしょう。
- むし歯が全身の健康に影響を与えることはありますか?
- むし歯を放置していると、菌血症や敗血症、感染性心内膜炎といった全身の病気を引き起こすことがあります。むし歯菌が血管のなかに侵入することが原因です。場合によっては命に関わるような状態にもなるため、早期に対処するのが望ましいです。
放置したむし歯の治療方法
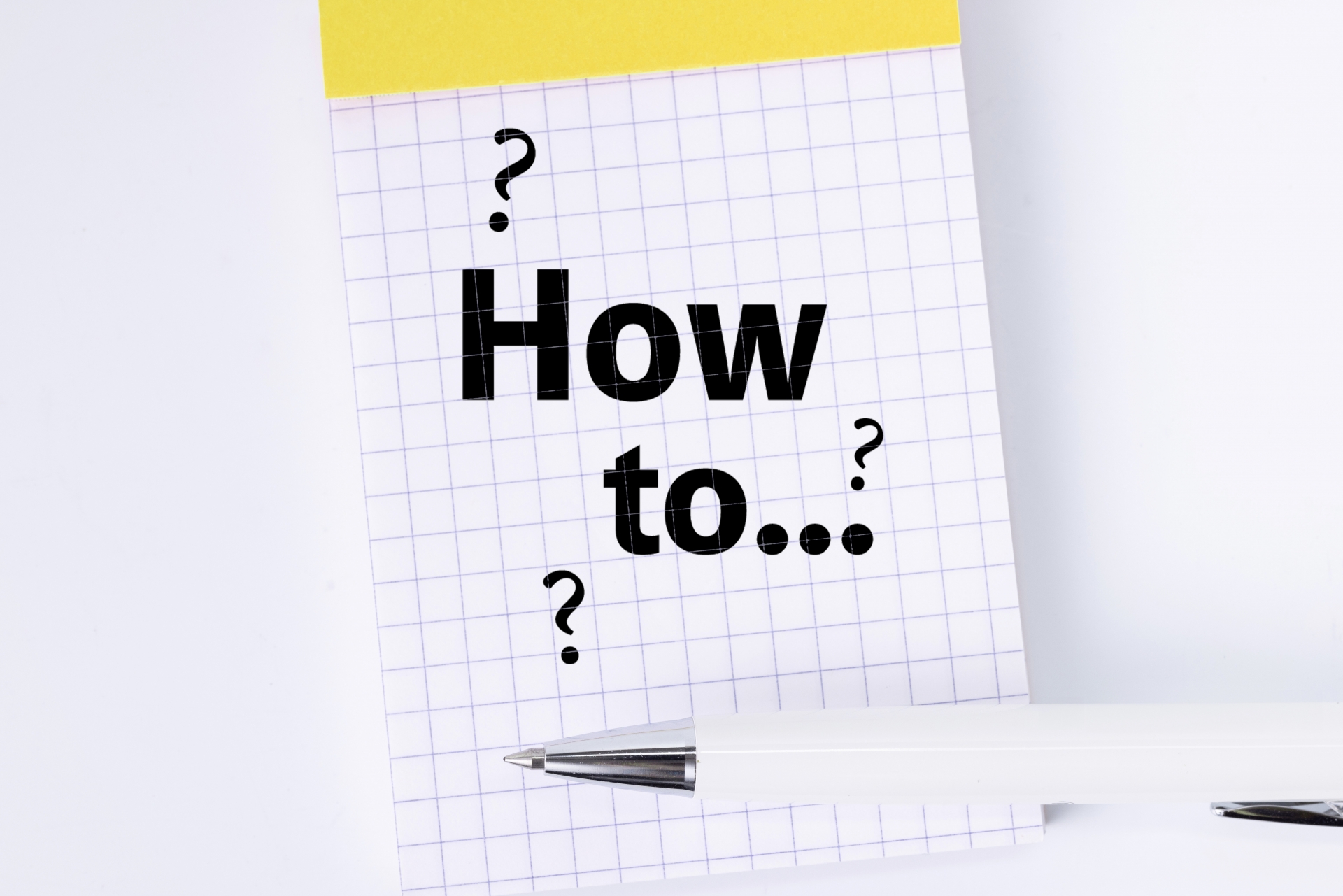 放置したむし歯を治す方法や進行させないための注意点を解説します。
放置したむし歯を治す方法や進行させないための注意点を解説します。
- 進行度別にむし歯の治療方法を教えてください
- むし歯の治療方法は、進行度によって変わります。
◎CO:歯の再石灰化を促す
歯を削らずに、フッ素による再石灰化作用でむし歯の進行を止めます。歯科医院でのフッ素塗布を定期的に受けて、セルフケアでもフッ素入り歯磨き粉を活用します。
◎C1:コンポジットレジン(CR)充填
感染した歯質を削って、コンポジットレジンで修復します。むし歯の深さや大きさ、部位によっては詰め物が必要になることもあります。
◎C2:CR充填、詰め物、被せ物
感染した歯質を削って、詰め物や被せ物で補います。場合によってはコンポジットレジン充填で対応できることもあります。
◎C3:抜髄、根管治療、被せ物
感染した歯髄を抜き取り、根管内をきれいに清掃します。仕上げは被せ物を装着します。
◎C4:抜髄・根管治療or抜歯
歯を保存できる場合は、抜髄と根管治療を行います。歯の保存が難しい場合は、抜歯をして補綴装置を装着します。
- C3やC4のむし歯でも歯を残すことはできますか?
- むし歯の状態によっては、歯を残すことが可能です。ただし、歯科医師の技術や知識、医療設備によっては、抜歯せざるをえないこともあるため、歯科医院選びは慎重に行いましょう。
- むし歯を進行させないために気をつけた方がいいことを教えてください
- 歯科検診を定期的に受けることで、むし歯を早期に発見できます。歯科医師のチェックがあれば、むし歯を治療せずに放置することも少ないため、3〜6ヵ月に1回の定期検診は受けるようにしましょう。自分でも歯の症状に気付いたら、すぐに歯科を受診することが大切です。
編集部まとめ
むし歯を放置することで生じる症状やリスクについて解説しました。進行性の病気であるむし歯は、放置すると症状が悪化していきます。重症例では、歯そのものを失うだけでなく、顎骨骨髄炎や蜂窩織炎、感染性心内膜炎といった深刻な病気を誘発することもあるため、むし歯を放置するのはNGです。また、むし歯の発生を見過ごさないためにも、毎日鏡で歯の健康状態を確認するとともに、歯科検診を定期的に受けるようにしてください。
参考文献
