智歯(親知らず)が原因で起こる智歯周囲炎は、強い痛みや腫れを伴うことがあります。
通常は痛み止めで症状が緩和されますが、効かない場合もあり、日常生活に支障をきたす恐れもあるでしょう。
智歯は、一般的に成人してから生える奥歯です。顎の骨のスペース不足や歯の向きの異常により、正常に生えないことがあります。
歯茎の一部に埋まったままだったり、横向きに生えていたりすると、周囲の歯肉に炎症を起こします。それが、智歯周囲炎の原因です。
本記事では、智歯周囲炎の痛み止めが効かない場合の対処法や治療法、予防ポイントを解説します。
智歯周囲炎で生じる症状

智歯周囲炎(ちししゅういえん)とは、智歯(親知らず)の周囲に炎症が起こる状態です。
特に20歳前後に発症しやすく、智歯が完全に生えきらないことで、歯と歯茎のすき間(歯周ポケット)に細菌が溜まりやすくなります。
智歯周囲はお口の奥に位置するため、きれいに磨くことが難しいことも炎症を起こしやすい原因です。
智歯周囲炎は、初期にはほとんど症状が見られないとされています。しかし睡眠不足や体調不良、過労などで急性期に進行し、強い痛みや腫れを引き起こすことも少なくありません。
ここでは、急性期に見られる智歯周囲炎の代表的な症状を解説します。
お口を開けづらくなる
炎症により智歯周囲の歯茎が腫れるため、お口が開けづらくなることがあります。他人が見ても腫れていることがわかることもある状態です。
またうえの智歯が正常に生えていない場合は、顎の骨にぶつかることで、お口の開閉時に引っかかるような違和感を覚えることがあります。
飲み込むときに痛みが生じる

炎症が喉や耳の奥、お顔の筋肉などに広がると、食べ物やつばを飲み込むときに痛みが生じることがあります。
飲み込む動作そのものが辛くなり、自然と食事を避けようとする方もいるでしょう。その結果、脱水や栄養不足に陥るリスクが高まります。
痛みでで飲食が辛くなった場合は早めに歯科医院を受診し、炎症の拡大を防ぎましょう。
噛むと痛い
炎症があると、硬いものを噛む際に強い痛みが生じることがあります。歯茎を軽く触っても痛みが生じ、膿が出る場合もあります。
また開けづらいお口を無理やり動かそうとすると、顎や頬に筋肉痛を感じることもあるでしょう。
さらに、上下の智歯が歯茎をはさみこむことで、圧迫による痛みを引き起こすこともあります。
顎下が痛くなる
智歯周囲炎が重症化し炎症が深部まで広がると、顎の下や首にかけて痛みや腫れを感じることがあります。
これは頬部蜂窩織炎(きょうぶほうかしきえん)という状態で、細菌感染が周囲の組織に広がった状態です。
熱が出る
炎症が全身に及ぶと、38度以上の熱が出ることがあります。重症化すると、敗血症という命に危険を及ぼす状態になることがあります。
発熱だけでなく寒気、だるさなどの症状がある場合は、速やかに医療機関を受診することが必要です。
智歯周囲炎で痛み止めが効かない原因

智歯周囲炎の痛みには、痛み止めが投与されることが一般的ですが、効かない場合もあります。
効かない原因として挙げられるのは、以下のとおりです。
- 患部に膿が溜まっている
- 炎症が強すぎる
- 細菌感染が周囲の筋肉やリンパ節や顎の骨にまで広がっている
- 神経が強く刺激されている
- 痛み止めを適切に服用できていない
- 痛み止めが症状に合っていない
痛み止めを服用してもすぐに痛みが完全に消えるわけではありません。痛み止めの種類が合わない場合は、変更する必要があります。
しかし1~2日経っても効果が感じられない場合は、症状が進行していることも考えられます。場合によっては、歯肉弁切除や抜歯が必要です。
痛み止めが効かないからといって、歯科医師に指示された以上の量を服用することは控えましょう。自己判断せずに、歯科医院を受診することが重要です。
智歯周囲炎で痛み止めが効かない場合の対処法

智歯周囲炎で痛み止めが効かず、辛い痛みに悩まされる方は少なくありません。
そのような場合には、痛みや腫れを軽減させるために患部を冷やしたり、殺菌効果のあるうがいや丁寧な歯磨きをしたりなどが効果的です。
ここでは、それらの対処法について解説します。
患部を冷やす
炎症による腫れや痛みを和らげるには、患部を冷やすことが効果的です。水で濡らした冷たいタオルで氷を包み、頬の外側から冷やしましょう。冷却シートを使用しても構いません。
ただし冷やしすぎると血行が悪くなり治りを悪くする可能性もあるため、注意が必要です。違和感がある場合や判断に迷う場合は、早めに歯科医師に相談しましょう。
うがいや歯磨きをする
お口のなかを清潔に保つことは、炎症の悪化を防ぐうえで重要です。
殺菌作用が強く刺激が少ないうがい薬を使ったり、患部に触れないように注意しながら優しく丁寧に歯磨きしたりしましょう。
痛みがあるからと歯磨きを避けると、細菌が繁殖し、炎症が悪化する恐れがあります。
歯科医院を受診する
痛み止めを服用しても効果がなく痛みが我慢できない場合は、歯科医院を受診しましょう。炎症が悪化すると、入院治療が必要になる場合もあります。
ほとんどの場合は、適切な抗生物質や痛み止めの服用で数日以内に痛みは軽減します。数日経っても痛み止めが効かない場合や症状が悪化していると感じたら、我慢せずに歯科医師に相談することが重要です。
智歯周囲炎の治療法

智歯周囲炎の治療には、まず炎症を抑え、口腔内を清潔に保つことが基本です。炎症が起きている間は、無理に患部に触ったり刺激を与えたりすることは避け、安静に過ごすことが重要です。
治療法は、炎症の程度や智歯の位置、全身の健康状態などによって異なります。ここでは、主な治療法を詳しく解説します。
抗生物質の服用
智歯周囲炎が軽症の場合は、細菌感染を抑えるために抗生物質が処方されます。ペニシリン系やセフェム系などの抗生物質が使われることが多く、発熱や腫れ、膿の症状がある場合に有効です。
痛みが強い場合は痛み止めやうがい薬などを併用することで症状の緩和が期待できます。歯科医師はそのほかの症状に応じた必要な薬を処方するため、用法用量を適切に守ることが重要です。
通常、数日以内に腫れや痛みが治まることが一般的です。しかし、症状が改善せず高熱や重度の炎症がある場合は歯科医院を受診しましょう。入院治療が必要になることもあるため、注意が必要です。
歯肉弁切除
智歯は正常に生えてこない場合があるため、適切な歯磨きがしにくく、歯と歯肉の間に食べかすや汚れが留まることが少なくありません。
智歯が斜めに生えていて、一部だけが歯肉から出ている状態の場合、歯肉弁切除を行います。智歯を覆っている歯肉を切除し、正常の位置に生えてくる手助けをする処置です。
歯肉弁切除によって智歯が露出し、清掃しやすくなることで再発を防げます。
ただし、炎症が強い間はすぐに処置を行えません。まず抗生物質や痛み止めなどで症状が落ち着いてから、歯肉弁切除を受けるようにしましょう。
抜歯

一度起こした智歯の炎症は繰り返すことが多いため、症状の軽快後に抜歯することが治療法の一つです。智歯が正常に生えている場合は標準的な抜歯で済むため、局所麻酔をして抜歯を行います。
しかし智歯が骨や歯茎のなかに埋まっていたり、横向きや斜めに生えていたりする場合は、歯肉や骨を一部削って抜歯する必要があります。
抜歯後に腫れや痛みがひどくなる可能性があり、事前にリスクを確認しておくことが必要です。
糖尿病や心疾患などの持病のある患者さんや、智歯の状態によっては、入院や全身麻酔下での管理が必要になる場合があります。
ただし、すべての智歯が抜歯対象になるわけではありません。智歯が正常に生えていて噛み合わせに問題がない場合や、高齢者や基礎疾患のある方で抜歯のリスクが高い場合では必ずしも抜歯が必要でないケースもあります。
抜歯を選択するかどうかは、慎重に判断されます。口腔内の状態や生活環境、将来のリスクなどを考慮して治療法を選択することが重要です。
智歯周囲炎になった場合に避けるべきこと

智歯周囲炎になった場合は、次のような行動はできる限り避けましょう。
- 強くうがいをする
- 強く歯磨きをする
- 患部を触る
- 激しい運動をする
- 長時間入浴する
- 飲酒する
- 喫煙する
- 刺激物や硬いもの、熱すぎるものを飲食する
うがい薬は口腔内を清潔に保つのに有効ですが、強くうがいをせず、軽くゆすぐ程度にしましょう。
歯磨きをする際は、炎症部位を強く磨くと傷つけてしまい悪化につながる恐れがあります。やわらかい歯ブラシを使い、優しく丁寧に磨くようにしましょう。
痛みや違和感があると舌や指で触れたくなりますが、細菌感染を広げたり炎症を悪化させたりすることにつながります。患部にはできるだけ触れないようにしましょう。
運動や入浴は血行を促進し、炎症を悪化させる原因になるため、できる限り安静に過ごすことが重要です。
飲酒と喫煙も血行を促進させます。炎症を悪化させるうえに、痛み止めや抗生物質の効果に悪影響を与える恐れがあるため、控えることが必要です。
辛いものや硬いもの、熱い食べものなどは、患部に負担をかける可能性があります。おかゆやスープなど、やわらかいものや刺激の少ない食事を選ぶようにしましょう。
智歯周囲炎を予防するためのポイント

智歯周囲炎は日頃から予防を意識することが重要です。予防するためのポイントは、以下のとおりです。
- 口腔内を清潔に保つ
- 免疫力を高める
- 歯科医院で定期検診を受ける
ここでは、予防するためのポイントをそれぞれ解説します。
口腔内を清潔に保つ
細菌が増殖しないために、口腔内を清潔に保つことが重要です。特に、智歯周囲は歯ブラシが届きにくく汚れが溜まりやすい場所です。
口腔内を清潔に保つための歯磨き方法としては、次の点が挙げられます。
- お口に合った歯ブラシを選ぶ
- コンパクトタイプのヘッドを選ぶ
- 一本ずつ丁寧に磨く
- 軽い力で小刻みに歯ブラシを動かして磨く
- お口を閉じ気味にして磨く
歯ブラシはさまざまな種類があるため、智歯用の歯ブラシを選ぶことが重要です。お口の奥にある智歯を磨くためには、ヘッドがコンパクトで薄いタイプが使いやすいでしょう。
しっかり磨いたつもりでも、磨き残している可能性があります。お口を閉じ気味にすると、奥まで歯ブラシの先が届きます。歯は一本ずつ丁寧に磨くよう心がけましょう。
また、定期的にデンタルフロスや歯間ブラシで歯間の汚れも除去したり、殺菌成分の入ったうがい薬を使ったりすることが効果的です。
免疫力を高める

智歯周囲炎は、風邪を引いたり疲労が蓄積したりなど、免疫力が低下していると炎症が起こりやすいとされています。
免疫力を高める方法は、以下のとおりです。
- 睡眠の質を高める
- ストレスを溜めない
- 適度に運動する
- 身体を温める
- 1日3食バランスのよい食事を摂る
- 腸内環境を整える
免疫力を高めると、智歯周囲炎を予防できるだけでなく、健康を維持できます。健康に過ごすために、日頃から免疫力を高めることを心がけましょう。
歯科医院で定期検診を受ける
智歯周囲炎の初期や慢性期では、自覚症状に気付きにくい場合があります。そのため、歯科医院で定期検診を受けることが重要です。
定期検診ではレントゲンを撮影して、智歯の位置と生えている向き、ほかの歯に影響を与えていないかを確認します。
歯茎が腫れている場合は、感染や炎症が起きている可能性が考えられるため、炎症や感染の有無や歯列への影響などもチェックします。さらに、むし歯や歯周病のリスク評価も重要です。
智歯の状態によっては、抜歯や適切な口腔ケアなどが必要です。症状がなくても口腔クリーニングを受けることで、お口のなかを清潔に保つことができます。
もし症状が現れた場合は放置せずに、早めに歯科医院を受診し、適切な処置を受けましょう。また、智歯をはじめとしてお口のことでお悩みの場合は、歯科医師に相談することをおすすめします。
まとめ
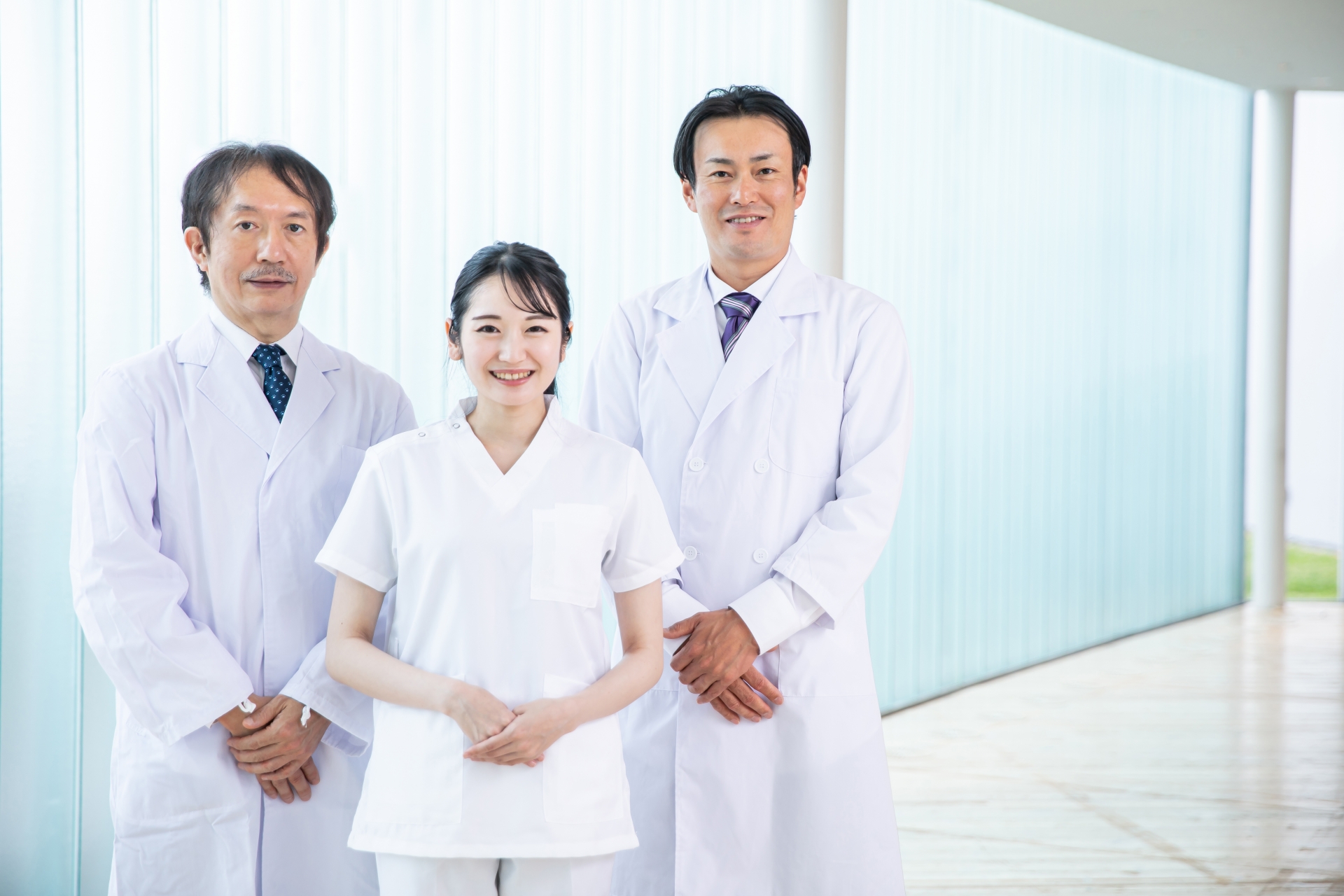
智歯周囲炎の初期段階ではほとんど自覚症状がないことが一般的です。しかし、風邪やストレスなどで免疫力が低下すると、急に症状が現れることがあります。
お口を開けづらくなったり、飲み込むときに痛みが生じたりするなど、日常生活にも支障をきたすことも少なくありません。
軽度であれば、抗生物質や痛み止めの服用によって、数日で症状が治まることが一般的です。ただし、なかには痛み止めが効かない場合もあります。
そのようなときは患部を冷やしたり、うがいや丁寧な歯磨きなどで口腔内を清潔に保ったりすることで症状の軽減ができます。
ただし自己判断で我慢して症状を放置すると、悪化するリスクがあるため、注意が必要です。
お口に違和感や気になる症状がある場合は、早めに歯科医院を受診し、適切な処置を受けるようにしましょう。
参考文献
