むし歯は身近な病気です。子どもから高齢の方まで、年代を問わず発症する可能性があり、20歳以上の9割程度がむし歯を経験しているとされています。むし歯を放置すると痛みや腫れが生じるだけでなく、食事や会話など日常生活に支障をきたすこともあります。さらに、重症化すると全身の健康に影響を及ぼす可能性もあるため、単なる歯の問題として軽視することはできません。本記事では、むし歯の基礎知識から進行の特徴、検査方法、治療法を解説します。
むし歯の基礎知識

むし歯は、お口の中で起こる微細な化学反応や、日々の生活習慣の積み重ねによって進行する病気です。最初は目立った症状がなくても、知らないうちに進行していることがあります。ここからは、むし歯の症状と原因を解説します。
むし歯の症状
むし歯は進行に伴って症状が変化する病気です。初期には痛みや違和感がほとんどなく、自覚するのが難しい場合が多くあります。最初の兆候として、歯の表面が白く濁って見える白濁(ホワイトスポット)が現れることがあります。これは、エナメル質の表面が酸によって溶け始めることで光の反射が変化するためです。日常生活に支障はなく、歯科検診で指摘されて初めて気付くことも少なくありません。
むし歯が進行すると、冷たい飲み物や甘い物をお口にした際にしみる感覚が現れます。これは、歯の内部にある象牙質が刺激を神経に伝えやすくなるためです。さらに進行すると、温かい物でも痛みを感じるようになり、ズキズキとした持続的な痛みや、夜間に眠れないほどの強い痛みが生じることもあります。この段階では、食事や会話など日常生活に大きな影響が及ぶこともあります。
重度になると、歯が欠けて噛む力を失うだけでなく、炎症が歯の根から顎骨へ広がる可能性があります。さらに、細菌が血液を通じて全身に広がると、発熱や倦怠感などの全身症状を引き起こすこともあります。つまり、むし歯はお口だけでなく、全身の健康にも影響を及ぼす病気といえます。
むし歯の原因
むし歯は偶然できるものではなく、いくつかの原因が関わって発生する病気です。特に重要とされているのは以下の4つです。
- 細菌
- 糖質
- 歯の質
- 時間
まず、むし歯の原因として大きな役割を持つのが細菌です。お口のなかにはミュータンス菌という細菌が存在し、食べ物や飲み物に含まれる糖分をエサにして酸を作り出します。この酸が歯の表面を少しずつ溶かしていきます。
次に関わるのが糖質(甘い物)です。チョコレートやお菓子、ジュースなどを摂取すると、お口の中は長時間酸性の状態になり、歯がダメージを受けやすい状況が続きます。
また、歯の質そのものにも個人差があります。エナメル質が厚くて丈夫な方もいれば、薄くてもろい方もいます。また、歯の質には唾液の働きも含まれます。唾液には酸を中和する力や、歯を修復する成分を届ける働きがあります。しかし、もともと唾液が少ない方や、加齢や薬の副作用などでお口が乾きやすい場合は、この防御力が弱まり、むし歯になる可能性が高まります。
そして最後に関わるのが時間です。酸が歯を溶かすスピードに対して、唾液による緩衝が追いつかなければ、むし歯は進行してしまいます。つまり、甘い物を食べてもすぐに歯を磨く、食べる時間を工夫するなどを意識することで、むし歯の可能性を抑えることができます。
このように、むし歯は甘い物を食べすぎた、歯みがきが足りないといった単純な理由だけでなく、細菌、食生活、体質、生活リズムなど、複数の要因が絡み合って発症する病気だといえます。
むし歯の段階別|特徴と自覚症状

むし歯は進行度によってCO(要観察歯)からC4までの段階に分類されます。これは歯科診療で広く用いられる指標であり、各段階ごとに見た目の特徴や自覚症状、治療法が異なります。ここでは、それぞれの段階における特徴と症状について解説します。
CO:要観察歯
CO(シーオー)はCaries Observationの略で、むし歯が始まる直前の状態を指します。エナメル質の表面が酸によって溶け始め、白く濁って見える、光沢が失われるのが特徴です。穴は開いておらず、痛みやシミる感覚もありません。
この段階では治療は不要ですが、定期的な経過観察が推奨されます。生活習慣を見直すことで、健康な状態に戻せる可能性が高い段階です。
C1:エナメル質のむし歯
C1は歯の外側にある硬いエナメル質に限局したむし歯です。歯の表面がザラつく、シミや小さな黒い点が現れることがありますが、神経には達していないため、痛みはほとんどないといわれています。
この段階でも自覚は難しく、定期健診で発見されることがほとんどです。早期に治療すれば削る量はごくわずかで済み、歯をほぼ残した状態で治療が可能です。
C2:象牙質まで進行したむし歯
C2はエナメル質の内側にある象牙質までむし歯が広がった状態です。象牙質はエナメル質よりもやわらかく、酸に溶けやすいため、進行が早いのが特徴です。
この段階では、冷たい飲み物や甘いものをお口に入れるとシミるようになり、食べ物を噛んだ際に痛みを感じることもあります。見た目は小さな穴でも、内部では大きく広がっている場合があり、正確な診断にはレントゲン検査が必要です。
C3:神経まで進んだむし歯
C3では、むし歯が歯の神経(歯髄)にまで達した状態です。ズキズキとした強い痛み、冷たいものや熱いものがしみる感覚、さらに何もしていなくても痛む自発痛が特徴です。これらの痛みは夜眠れないほど強いことがあり、食事や会話が難しくなるなど、日常生活に大きな影響を及ぼします。
この段階を放置すると、炎症が進行して歯の神経が死んでしまい、その後に感染が歯の根の先へ広がって膿がたまることがあります。これを根尖性歯周炎と呼び、顔の腫れやリンパ節の腫れ、発熱を伴う場合もあります。
C4:ほとんど歯が失われたむし歯
C4はむし歯の最終段階で、歯の大部分が崩れ、根だけが残った状態です。神経がすでに死んでいることが多く、強い痛みが一時的に消える場合もありますが、細菌は根の周囲に広がり続け、慢性的な感染源となってしまいます。その結果、顎骨炎や全身への感染を引き起こす可能性が高まります。
外見上は歯が欠けて根だけが残っているため、噛む力が著しく低下します。これにより食事が制限されるだけでなく、会話がしづらくなるなど、日常生活全般に影響が生じます。
むし歯の段階を調べる方法
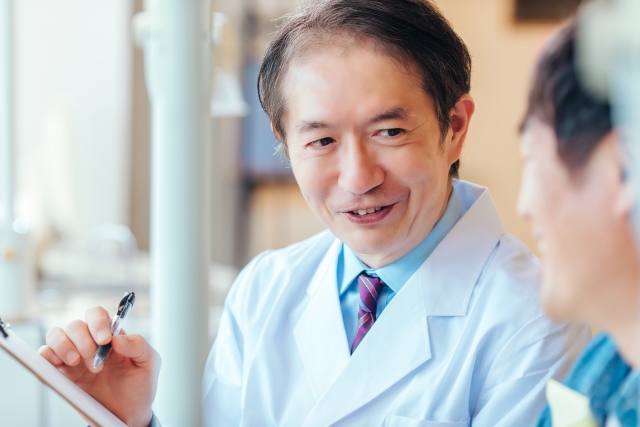
むし歯は、自覚症状とむし歯の進行度が一致しない場合も多く、早い段階で自分自身で気付くのは難しいのが実情です。ここでは、自分で確認できる範囲と、歯科医院で行われる診断方法を解説します。
自分でむし歯の段階を確認することはできる?
自分でのチェックはあくまで異常に気付くきっかけ程度にすぎず、進行度や治療の必要性を正確に判断する手段にはなりません。
とはいえ、自宅でもある程度の確認は可能です。例えば、鏡を使って歯を確認し、歯の表面に黒い点や白く濁った部分が見える場合は、むし歯の可能性があります。ただし、黒く見えても単なる着色の場合もあり、必ずしも進行したむし歯とは限りません。逆に、見た目がきれいでも歯と歯の間や裏側でむし歯が進行していることもあります。
また、症状から気付く場合もあります。例えば、冷たいものがしみる、噛むと痛いといった症状は、むし歯を疑うきっかけの1つです。ただし、これらの症状は知覚過敏や歯周病などでも似たような感覚が生じるため、自己判断には限界があります。
歯科医院でむし歯の段階を確認する方法
歯科医院では、まず歯科医師による視診と触診が行われます。専用のライトで歯の表面を確認し、色や光沢、白濁、小さな穴の有無などをチェックします。必要に応じて、探針と呼ばれる器具で歯の溝を軽く触れ、ざらつきや軟化の有無を確認することもあります。
さらに詳細な評価のためにレントゲン検査が用いられます。レントゲンは歯と歯の間や奥深くに隠れたむし歯を発見するのに有効で、特にC2以降の象牙質に達したむし歯の診断に役立ちます。表面の変化がわずかでも、内部で大きく進行しているむし歯の状態がレントゲンによって明らかになることもあります。
むし歯の段階別|治療法

むし歯の治療は、段階によって大きく内容が変わります。初期段階であれば削らずに管理できることもありますが、進行して神経まで達すると、長期間の治療や抜歯が必要になる場合もあります。ここでは、各段階ごとの治療法を解説します。
COの治療法
COは穴が開く前の初期段階であり、削らずに治療できる可能性が高い状態です。フッ素を塗布して歯を強化したり、再石灰化を促したりする処置が行われます。また、むし歯になりやすい歯の溝をプラスチックで保護するシーラント処置が行われることもあります。
併せて、生活習慣の見直しも重要です。甘い物や間食の制限、就寝前の飲食を控えること、正しい歯磨き方法などについて指導が行われます。
C1の治療法
C1の段階でも、穴がごく小さく清掃状態が良好であれば、削らずに経過観察することが可能です。フッ素やシーラントによって進行を抑える処置が行われます。一方、むし歯が進行しやすい部位や食べ物が詰まりやすい箇所では、むし歯部分を最小限に削り、歯と同じ色の樹脂(コンポジットレジン)を詰める治療が一般的です。
近年では、最小限の介入(Minimal Intervention=MI)という考え方が重視されており、健康な歯をできるだけ残す治療が基本となっています。そのため、大きく削る必要はなく、歯を元の形に近い状態で長く保つことが可能です。
参照:『Minimal intervention dentistry for managing dental caries – a review』(International Dental Journal)
C2の治療法
C2では、エナメル質の内側にある象牙質までむし歯が達しているため、削って詰め物をする治療が必要です。むし歯の範囲が小さい場合はコンポジットレジン(歯の色に近い樹脂素材)で対応できますが、範囲が広い場合や噛み合わせの力が強くかかる部位では、型を取ってインレーやオンレーといった詰め物を作成します。この段階で治療を行えば、神経を残せる可能性が高く、歯の寿命を延ばすことにつながります。
C3の治療法
C3では根管治療が必要です。細菌によって炎症や感染を起こした神経(歯髄)を取り除き、歯の根の内部(根管)を洗浄、消毒したうえで、再び菌が侵入しないように薬剤を詰めます。治療後は歯がもろくなっているため、クラウン(かぶせ物)を装着して歯を保護します。
なお、神経が保存可能と判断された場合には、MTA(Mineral Trioxide Aggregate)という特殊なセメントを用いた生活歯髄療法が適応されることもあります。これは神経を部分的に残す治療法のことです。
C4の治療法
C4は歯の大部分が崩れ、根だけが残った状態です。この段階では歯を保存するのが難しく、抜歯が選択されることが一般的です。抜歯後はそのままにせず、ブリッジ、入れ歯、インプラントなどによって噛む機能を回復させます。どの治療法を選ぶかは、歯の状態や生活習慣、患者さんの希望によって決まります。
ただし、C4だからといって必ず抜歯になるわけではありません。歯の状態によっては保存を試みることもあり、最終的に保存が困難と判断された場合に抜歯を選択します。
まとめ

むし歯は、はお口の中で起こる化学反応や日々の生活習慣が積み重なることで進行する病気です。初期段階では痛みがなく、自分で気付くことが難しいため、発見が遅れることも少なくありません。
COやC1のような初期段階であれば、生活習慣の改善や簡単な処置によって進行を食い止めることが可能です。しかし、C2以降になると、しみる、痛むといった症状が現れ、治療内容もより複雑になっていきます。C3で神経に達すると強い痛みや膿の形成につながり、C4に至ると抜歯が避けられない場合もあります。
さらに、重度のむし歯は顎や全身に炎症を広げる危険性もあるため、単なる歯の問題として軽視することはできません。鏡を使ったセルフチェックも異常に気付くきっかけの1つですが、正確な診断には歯科医院での検査が欠かせません。
定期的な歯科検診によって早期発見、早期治療につなげることが、歯の寿命と全身の健康を守るための有効な手段といえます。
参考文献
- 『大人のむし歯の特徴と有病状況』(厚生労働省)
- 『19.う蝕(虫歯)』(愛知県薬剤師会)
- 『歯とお口のことなら何でもわかる テーマパーク8020(むし歯)』(日本歯科医師会)
- 『よい歯のABC』(石川県歯科医師会)
- 『歯内療法とは』(一般社団法人 日本歯内療法学会)
- 『口腔外科相談室』(公益社団法人 日本口腔外科学会)
- 『う蝕治療ガイドライン 第2版』(特定非営利活動法人 日本歯科保存学会)
- 『Minimal intervention dentistry for managing dental caries – a review』(International Dental Journal)
- 『歯髄保護の診療ガイドライン』(日本歯科保存学会)
