「健康診断は毎年受けてるけど、歯の健診はしばらく行ってない」そんな方も少なくないでしょう。
近年、日本政府が掲げる国民皆歯科健診が注目を集めています。これは、すべての国民が定期的に歯科健診を受けることを目指す制度で、むし歯や歯周病の早期発見だけでなく全身の健康管理や医療費削減にもつながる重要な取り組みです。
この記事では国民皆歯科健診とは何か、実際に義務化された場合に企業や個人にどのような影響があるのか、わかりやすく解説していきます。
歯科健診が義務化される背景

歯科健診の義務化が検討されている背景にはどのような経緯があるのでしょうか。ここでは、その理由について詳しく見ていきましょう。
口腔内の環境悪化が全身の健康状態に影響するため
歯周病をはじめとする口腔内の疾患は、単なるお口のトラブルにとどまりません。歯の健康と全身の健康には大きな相関関係があることが近年の研究でわかってきました。
歯周病やむし歯などでお口のなかが炎症を起こすと、炎症によって出てくる毒性物質が歯肉の血管から全身に入り、さまざまな病気を引き起こしたり悪化させたりする原因となるのです。
この炎症性物質は、心筋梗塞や脳梗塞、糖尿病、認知症、誤嚥性肺炎などといった重篤な全身疾患のリスクが高まることが明らかになっています。
また、歯が抜けたり、噛む力が弱まったりすると食べられるものが限られてしまい栄養のバランスが崩れる原因にもなります。
つまり、歯の健康を維持することは、全身の健康を守るうえでもとても大切なことなのです。
歯科健診の受診率が低いため
医科健診や人間ドックの受診は広く浸透していますが、歯科健診については歯が痛くなってから歯医者に行く方が多く、予防のために通うという習慣は十分には広まっていないのが現状です。
現在の制度でも、ライフステージごとに一定の歯科健診の機会は設けられています。
例えば、1歳6ヶ月や3歳児には自治体による乳幼児健診の一環として歯科健診が実施され、小・中・高校生は学校保健安全法に基づき年に1回以上の学校歯科健診が義務化されています。
しかし、問題は成人以降です。就職後、企業による定期健康診断では、原則として歯科健診は含まれていません。一部の企業が福利厚生として独自に実施する例はあるものの、全国的に見ればごくわずかです。
また、妊婦には自治体による歯科健診の補助制度が設けられているケースもありますが、対象となる方や実施内容にはばらつきがあります。
高齢者においても同様です。75歳以上の後期高齢者を対象とした歯科健診は、一部自治体で導入されていますが、任意であり受診率が高いとはいえません。
実際に、2022年度の歯科疾患実態調査結果によると、過去1年間に歯科健診を受けた者は約58.0%でした。特に30歳~50歳の男性は30%~40%と歯科受診している方が低い傾向にありました。
このように、日本の歯科健診制度は成人前の年代に集中しており、成人以降の歯科健診体制が手薄な点が問題視されています。だからこそ、生涯にわたって歯科健診を義務化する方針が検討されています。
国の医療費を削減するため
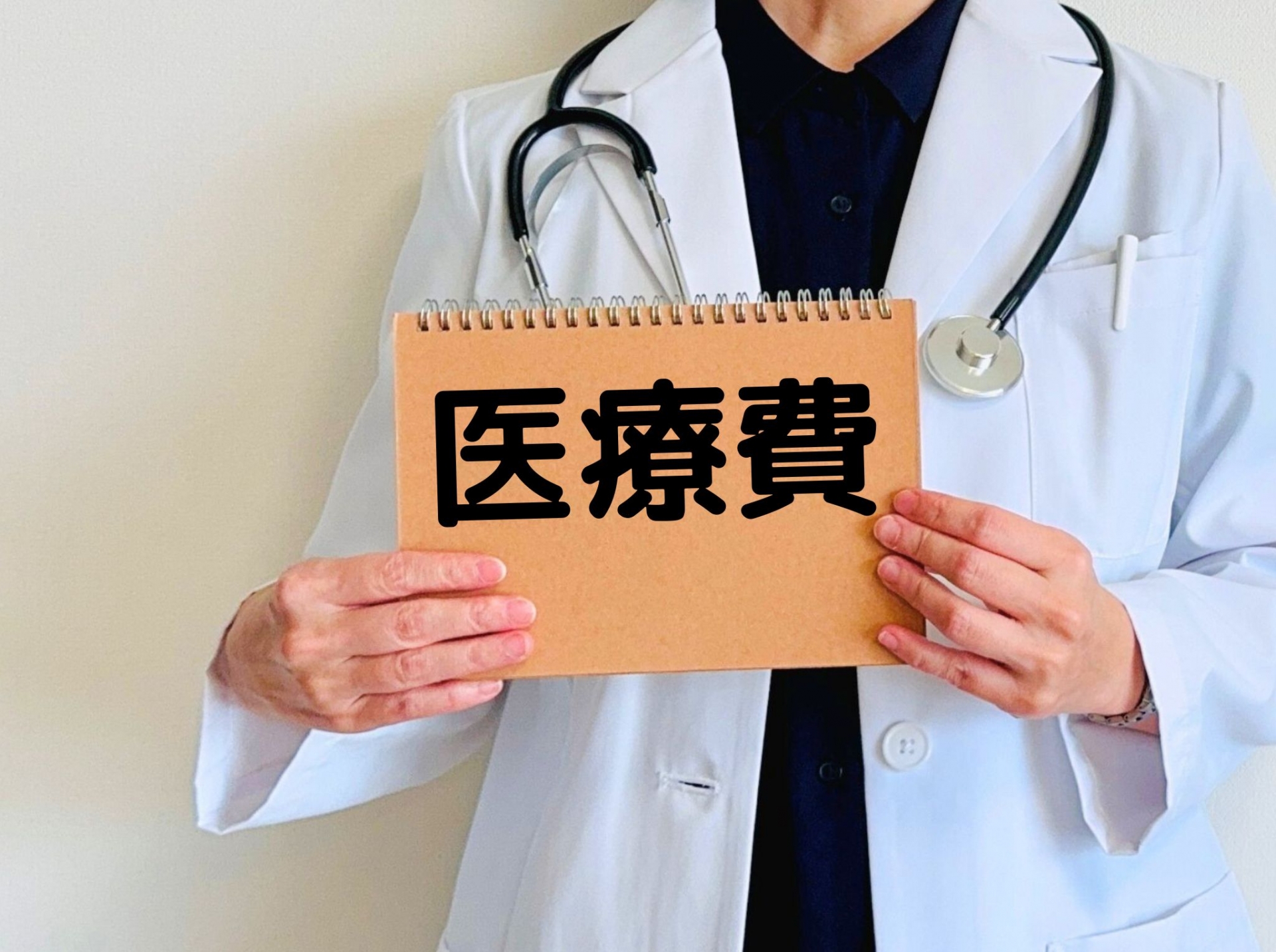
高齢化が進む日本では、年々ふくらむ医療費が深刻な課題となっています。
2022年9月の総務省の推計によると、65歳以上の高齢者は日本の総人口の29.1%を占めており、その高齢者層による医療費の支出は国全体の医療費の61.2%(2022年度)に達しています。つまり、高齢者の健康状態は、日本の医療財政に直結する問題です。
そうしたなかで注目されているのが、歯の健康と全身の健康との関係です。近年の研究では、歯の本数が少なくない方ほど医科の受診費用が低いという傾向が報告されており、歯の本数が少ない方では医療費が約1.3倍高くなるというデータもあります。
また、歯周病治療によって糖尿病の患者さんの血糖コントロール(HbA1c)が0.4〜0.66%改善するという研究報告もあり、これは医科の治療負担を軽減し間接的に医療費の削減につながる可能性を示唆しています。
さらに、高齢者施設での継続的な口腔ケアによって誤嚥性肺炎の発症率が約60%減少、入院日数が約25%短縮されたとの研究結果も示されました。これらは、口腔ケアが高齢者の健康維持に寄与し、結果として医療資源の効率的活用につながることを示しています。
こうした背景から、国民皆歯科健診は単なるむし歯と歯周病予防にとどまらず、全身の健康維持や将来的な医療費の削減を見据えた国家的な健康戦略のひとつとして期待されています。
国民皆歯科健診の内容

ここからは、国民皆歯科健診の内容について解説します。
概要
国民皆歯科健診とは、すべての国民が生涯を通じて定期的に歯科健診を受けられるようにすることを目指した制度です。
現在歯科健診が義務化されているのは、1歳6ヶ月と3歳の幼児や小学校1年生~高校3年生までの学生、そして身体に有害な物質を発散する化学工業などの一部の業種で働く方たちのみに限られています。
そのため、大学生や社会人、高齢者などは歯科医院を受診する機会が少ないことが現状です。
国民皆歯科健診はそういった健診の空白の世代にも歯科健診を義務化することで、むし歯や歯周病の早期発見と予防を促し、年齢を重ねても健康な歯で過ごせるようにすることが目的です。
また、むし歯や歯周病を防ぐだけでなく、全身の健康維持にもつなげていく狙いがあります。
お口の健康は、食べることや話すこと、笑うことなど毎日の暮らしに大きく関わっています。だからこそ、歯科健診も医科健診と同じくらい、当たり前の習慣として根づいていくことが必要です。
義務化される時期
経済財政運営と改革の基本方針2025にも明記されているとおり、政府は2025年度中の国民皆歯科健診導入を目標に準備を進めています。ただし、現時点では具体的な時期やスケジュールは、まだ確定していません。
企業や自治体における実施方法やスタート時期、国民への周知方法などについては、今後段階的に公表されていくことが見込まれます。制度の動向を正しく把握するためにも、政府の発表や関連情報をこまめにチェックしておくとよいでしょう。
費用

費用負担に関してはまだはっきりと決まっていません。現在の歯科健診は健康保険適用後で2,500~3,000円ほどです。
国民皆歯科健診として導入される場合は費用負担を国や健康保険などがカバーする方向で検討中とされていますが、自治体や企業、個人の負担割合などはまだ決まっていません。
検討されている国民皆歯科健診の検査項目

それでは国民皆歯科健診として検討されている検査項目には、どのようなものがあるのでしょうか。以下に検討されている検査項目について詳しく解説します。
問診
ご自身の歯や全身の健康状態を把握するため、簡単なアンケートのような問診を実施します。具体的には、以下のような項目があげられます。
- 歯茎の出血、腫れ、口臭などの自覚症状の有無
- 全身疾患(糖尿病、心疾患など)の有無
- 生活習慣(喫煙、飲酒)
- 過去の歯科受診状況
- 口腔ケアの実施状況(歯磨き回数、補助清掃用具の使用の有無など)
これらは歯周病と深く関係しているため、大切なチェックポイントとなります。
口腔内のチェック

口腔内のチェック項目には、以下のようなものがあります。
- むし歯の有無や進行状況
- 歯茎の状態
- 歯石(しせき:歯にこびりついた汚れ)がたまっていないか
- 歯の汚れ具合
- 顎の動き
- お口のなかの粘膜に異常がないか
これらの検査項目は、口腔内の健康状態を総合的に把握するために欠かせないものであり、早期発見や早期治療に役立つ重要なポイントです。
歯周病の進行度の診断
歯周病の進行状況を調べるために、歯と歯茎の間の歯周ポケットの深さを専用の器具で測定します。健康な歯茎では歯周ポケットは浅いですが、炎症が進むと深くなり、歯周病が進行しているサインです。
加えて、CPI(Community Periodontal Index)という国際的な評価基準を用いて、歯の状態を数値化します。これは歯茎からの出血や歯石の付着、ポケットの深さなどを総合的に評価し、歯周病の進行度を客観的に把握できる指標です。CPIは厚生労働省のガイドラインでも標準的な歯周病の評価方法として採用されています。
口腔ケアのアドバイス
健診結果に基づき、個人別にセルフケア改善や受診勧奨などの保健指導が実施されます。
アドバイスの内容は、歯の磨き方やデンタルフロスの活用といったセルフケア指導から、歯科医院での精密検査や治療受診の勧奨まで多岐にわたります。
国民皆歯科健診の重要性

ここまで、国民皆歯科健診が検討されている背景や、義務化された場合の制度の概要についてご紹介してきました。
では、もしこの制度が本当に義務化されたら、私たちの生活にはどのような影響があるのでしょうか?また、日本全体としては、どのようなメリットが期待できるのでしょうか?
国民皆歯科健診の義務化によってもたらされる可能性のある影響について、具体的に見ていきます。
受診率向上によって早期発見の増加につながる
2022年度のデータによると歯科健診の受診率は約58%であり、自治体による歯周疾患健診の受診率は約5%ととても低い水準です。
このように健診の受診が進まないと、むし歯や歯周病が見逃されて進行し、抜歯や全身疾患のリスクが高まります。
一方で、一部自治体の調査では定期的に歯科健診を受けている方ほど、口腔疾患が早い段階で見つかっているという調査結果も報告されました。
こうした背景から、すべての世代に定期的な歯科健診の機会を設ける国民皆歯科健診の導入が検討されています。早い段階での発見と治療が進めば、重症化を防ぎ、健康な生活を長く保つことが期待されています。
国民の健康寿命を延ばせる
一部地域で行われた大規模な住民調査によると、歯の本数が多く日頃から口腔ケアをしている方ほど、要介護や死亡のリスクが低いことが明らかになっています。
しっかり噛める状態を保つことは、食生活の質の維持にもつながり、結果として年齢を重ねても元気に過ごす助けになります。歯の健康を守ることは、単にお口のなかだけの問題ではなく、身体全体の健康や長く元気に暮らす力にも大きく関わる重要なポイントです。
国民全体で口腔ケアを習慣化することは、日本全体の健康寿命の底上げにつながる可能性があります。
予防治療の重要性を普及できる
定期的な歯科健診は、むし歯や歯周病の重症化を未然に防ぎ、高額な治療や抜歯リスクの回避につながります。
日本歯科医師会の調査によると、歯科健診を継続的に受けている方は、そうでない方に比べて年間で約20,000円も治療費が少ないというデータがあります。
健診時には歯石除去やフッ素塗布、歯磨き指導、生活習慣の改善提案などのサポートを受けられることも大きなメリットです。歯科医院に定期的に通うことでセルフケア能力が向上し、歯の健康に対する意識も高まるため、予防することが当たり前の習慣になっていくことが期待されます。
歯を失う可能性を減らせる
むし歯や歯周病は、放置してしまうと歯を失う原因になります。しかし、定期的な歯科健診と継続的なケアによって、それらの病気を早く見つけて進行を防ぐことが可能です。
実際に、80歳で20本の歯を保とうという8020運動において、定期健診の習慣がある方ほど自分の歯を長く保ちやすいという結果が報告されています。
しかし、残念ながら日本では欧米の先進国と比べて歯の健康に対する意識や定期健診の受診率は低く、高齢になったときに残っている歯の本数も少ないのが現状です。
だからこそ、すべての国民が定期的に歯科健診を受けられる国民皆歯科健診の導入が期待されています。この取り組みが広まれば、歯を失うリスクを減らし、いつまでも自分の歯で食事を楽しめる健康な生活につながります。
すでに義務化されている歯科特殊健康診断とは

歯科特殊健康診断は、塩酸やフッ化水素、硫酸など、歯や歯の支持組織に有害な化学物質を扱う労働者に対して、労働安全衛生法に基づいて義務化されている健診です。
この健診の対象となるのは、これらの物質のガスや蒸気、粉じんが発生する作業場に常時従事する労働者です。業務の性質上、歯の損耗や粘膜への障害といった健康被害のリスクが高いことから実施されています。
健診は雇い入れどきや配置転換時、その後6ヶ月ごとに実施し、歯科医師による診察と必要に応じた口腔写真撮影などが行われます。
違反時は500,000円以下の罰金が科される可能性があるにも関わらず、2020年に一部地域で行われた調査では、酸類を扱う事業場のうち実際に健診を実施していたのはわずか31.5%でした。制度の存在が十分に周知されておらず、運用面での課題も浮き彫りになっています。
国民皆歯科健診が義務化された場合に違反するとどうなる?

2025年6月の時点で、国民皆歯科健診はまだ義務化されておらず、実施方法や罰則といった具体的な制度内容は未確定です。しかし、今後もし義務化された場合は、現在の会社で行われている健康診断(医科健診)に近い仕組みになると考えられています。
例えば、企業には従業員に健康診断を受けさせる義務がありますが、これを怠った場合には500,000円以下の罰金や行政指導が科されます。歯科健診においても、労働安全衛生法に基づく措置として導入される可能性が高いと考えられるでしょう。
一方で、従業員や一般の個人が歯科健診を受けなかった場合は、医科健診と同様に個人に対して罰則が課される可能性は低いと考えられます。
まとめ

国民皆歯科健診の義務化については、未確定の部分も多く、今後の制度設計や議論の行方を見守る必要があります。しかし、制度の有無に関わらず、歯の健康は一人ひとりの生活や将来に関わる大切な問題です。
これまでは、歯が痛くなってから歯医者に行くという方も少なくありませんでした。しかし今後は、悪くなる前に歯科健診を受けるという予防的な受診を前提とした意識改革が、より一層求められていくでしょう。
制度の整備を待つだけでなく、まずは私たち一人ひとりが自分の歯を大切にする意識を持つことが、ご自身の将来の健康や医療費の抑制の第一歩となります。
参考文献
- 歯周病が全身に及ぼす影響|特定非営利活動法人 日本臨床歯周病学会
- 令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要
- 後期高齢者における歯数と医療費との関連
- 歯周病治療で血糖コントロールの改善を!|一般社団法人 播磨歯科医師会
- 介護職員が行う標準化された口腔ケアの入院予防効果および医療費削減効果の検証
- 口腔と全身の健康に関するエビデンスコラム集
- 職域等で活用するための
歯科口腔保健推進の手引き- 経済財政運営と改革の基本方針2025について
- 歯科診療報酬点数早見表
- 歯科口腔保健の推進に向けた取組等について
- 地域における高齢者の口腔・食支援の取組推進のためのハンドブック
- 「未来の歯産価値を、今からつくる。#投歯」PJ始動 歯科健診の有無が、将来的な医療費・介護費に影響|日本歯科医師会
- これからの8020|8020推進財団
- 一般健康診断に『歯科』を盛り込む必要性について
- 歯周病検診マニュアル2023
