もしも何らかの原因で一番奥の歯を失ってしまったらどのような治療を行うのかご存じでしょうか。
奥にもう歯がない状態のことを遊離端欠損といい、この状態を放置するとさまざまなリスクが起こる可能性が高くなります。
両側の奥歯を失った状態を両側遊離端欠損、片側のみを失った状態を片側遊離端欠損といいます。
本記事では片側遊離端義歯に焦点を当て、治療のメリット・デメリットを解説します。さらに具体的な義歯の作製期間や費用を保険適用の有無に分けて紹介します。
義歯(入れ歯)以外の対処法も紹介するため、奥歯を失ってしまったときにどの対処法が自分に合っているのかを判断する一助になれば幸いです。
片側遊離端義歯とは?

歯を失う原因はさまざまですが、厚生労働省によると、歯を失う二大原因はむし歯と歯周病です。
歯は一般的に奥歯から失われていく傾向にあり、一番奥の歯がない状態のことを遊離端欠損といいます。
片側の奥歯を失った際に使用する義歯を、片側遊離端義歯といい、一般的に入れ歯と呼ばれます。
通常の部分入れ歯は、前後の歯に引っかけることで安定します。しかし、片側遊離端では後ろの支えがないため、固定が難しくなるでしょう。
装着感や噛む力が通常の部分入れ歯とは異なる点が特徴です。
遊離端欠損への対処をしないとどうなる?
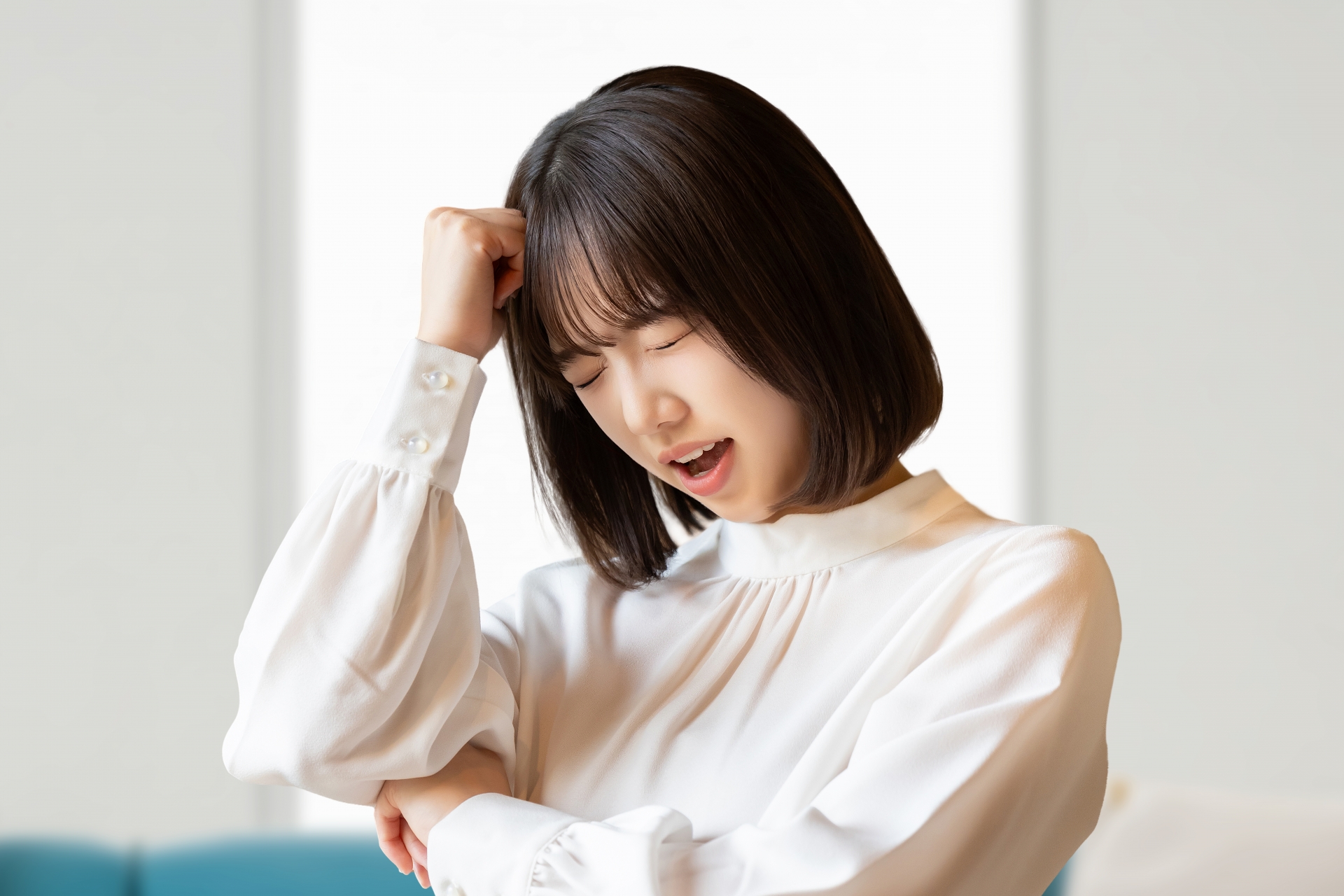
片側遊離端、つまり奥の歯がない状態を放置すると複数の問題が生じます。
歯を失うことで生じる一般的な影響は以下のとおりです。
- 抜けた歯の反対側で噛み合っていた歯が伸びてくる
- 噛み合わせが悪くなる
- むし歯や歯周病になりやすくなる
- 口元のしわが増える
- 見た目が悪くなる
- 発音がきちんとできなくなる
- 歯茎が下がってくる
- 食べ物をうまく噛みきれなくなる
遊離端欠損の場合は、歯並びが乱れたり噛み合わせが悪化したり、むし歯や歯周病のリスクが高まったりします。
ここでは遊離端欠損に絞って、問題点を一つずつ解説します。
歯並びが乱れる
遊離端欠損を放置して何の対処もしなければ、隣の歯が倒れてくる可能性が指摘されています。奥歯が失われると、その前方にある歯は噛み合わせを支持する力が弱くなり、より失われやすくなる悪循環を招きます。
奥歯を失うと、前歯への負担が増し、ぐらつく原因になります。
歯並びがきれいに保たれている要因は、隣同士の歯が支え合っていることが関係しているといわれています。
もしも歯が失われてしまった場合、そのバランスが崩れてしまうため、歯並びが乱れたり歯が傾いたりする原因になります。
噛み合わせが悪化する

上下の歯が正しく噛み合うことは、噛み合わせの維持に重要です。歯が欠損していると、欠損した上下反対側の歯が伸びてきてしまいます。
歯が伸びてきたり、抜けた歯の隣の歯が傾いたりすると、噛み合わせが崩れて悪化する可能性が高くなります。
さらに、欠損部分周辺の残存歯に過剰な力がかかってしまい、歯周病や歯の破折を引き起こしかねません。
噛み合わせが悪いと、肩・首・顎の周りの筋肉が緊張して、肩こりや頭痛の原因になることがあります。
悪い噛み合わせは、顎関節の負担になり、顎関節症の原因の一つになっていると考えられています。
むし歯・歯周病のリスクが高くなる
前述の歯並びや噛み合わせが悪化すると、歯間の清掃が困難です。その結果歯垢が蓄積してむし歯や歯周病のリスクを高めてしまいます。
歯と歯肉の間の清掃が行き届かないと、その部分に多くの細菌が停滞して歯肉の辺縁が炎症を起こして赤くなったり腫れたりします。
むし歯や歯周病を起こしている原因は、歯垢1mgのなかにいる約10億個の細菌です。特に歯周病を引き起こす細菌が多く存在しています。
歯垢が歯石になると自分の歯磨き方法では取り除けなくなるため、歯科医院でメンテナンスを受ける必要が出てきます。
歯周病は進行すると、膿が出たり歯が動揺したり、歯肉や歯を支える骨が溶けたりしてしまう病気です。悪化すると歯を抜かなければならなくなります。
片側遊離端義歯のメリット・デメリット

遊離端欠損の治療法の一つに遊離端義歯があります。ほかにも治療法はありますが、ここでは片側遊離端義歯のメリットとデメリットを保険適用の面や装着感などの観点から説明します。
メリット:健康保険が適用できる
義歯には健康保険が適用できるため、保険の負担割合内で治療を受けることができます。費用が抑えられて、経済的な負担が少なく治療が受けられるのがメリットです。
保険が適用できる義歯の種類にはアクリルレジンと呼ばれる歯科用プラスチックの材料が使われます。
部分入れ歯となる片側遊離端義歯は、歯列内に固定するためのクラスプと呼ばれるバネが使われており、保険適用の場合のクラスプは金属です。
メリット:健康な歯を大きく削る必要がない
片側遊離端義歯の場合は、後述するブリッジのように歯を大きく削る必要がないため、歯への負担が少なく済みます。
また、インプラント治療のような外科的処置を必要としないため、痛みや腫れや感染症など生体への侵襲が少なく済みます。
このように残存歯への影響をできるだけ小さく抑えることができるのが片側遊離端義歯のメリットです。
デメリット:安定性は高くない
通常の義歯と異なり、支える部分が片側しかないのが片側遊離端義歯の特徴です。そのため義歯を安定させるのが難しく、食事中に安定しないことが課題です。
特に硬い食べ物を食べるときに不安定になりやすい傾向があります。
素材はプラスチックでできているため、どうしても装着に違和感が残ります。
デメリット:噛む力は欠損部位の大きさとフィット感に左右される
フィット感や義歯への適応力は、患者さんの健康状態によって異なり、一般的に健康な人ほど適応しやすいとされています。
また、噛む力は欠損部位が小さければ安定し、欠損が大きければ義歯が不安定になり噛む力が弱くなります。
保険適用のアクリルレジン製義歯は、床部分が厚くなり、フィット感が低下しやすいといわれています。
片側遊離端義歯の作製期間

ここでは片側遊離端義歯の作製期間について解説します。保険適用の場合と自由診療の場合で、使用する材料や作製の工程に違いがあることから期間が異なっています。
期間が異なる理由や流れも含めて確認しましょう。
保険適用の場合
おおよそ2〜4週間かかり、調整が必要な場合は追加でさらに数回通院が必要になります。
一般的な作製の流れは次のとおりです。
- 初診・型取り
- 仮の義歯を合わせてから微調整する
- 完成
保険適用の義歯は、自由診療に比べて型取りが簡易的なため、完成後の装着感に違和感が出ることがあります。そのため、調整を繰り返しながら馴染ませていきます。
自由診療の場合
おおよそ2〜3ヶ月かかります。作製の流れは保険適用の場合と同じですが、保険診療よりも精密な型取りや高品質な素材を使用するため時間がかかります。
時間はかかりますが、よりお口にあった部分入れ歯を精密に作る分、完成後の調整は少なくすることが可能です。
片側遊離端義歯の費用の目安

片側遊離端義歯を作製するうえで大事なことの一つが費用です。それぞれの経済状況に合わせて自分に合った対処法を選ぶようにしましょう。
ここでは保険適用の場合と自由診療の場合の費用を比較して解説します。
保険適用の場合
保険適用の範囲内で義歯を作製する場合の費用は、5,000〜15,000円程度です。
素材はレジン(プラスチック)が使われ、装着感は床の部分に厚みを持たせるため、違和感が出ます。
保険適用で作製した義歯に関しては、気をつけるべき点があります。それは、義歯作製後6ヶ月間は作り直しができないことです。
義歯が破損した場合の対応については、国の規定がありますが、自治体によって例外が認められることもあります。
保険適用の入れ歯を自由診療で作り直す場合にはこのルールの制限は受けません。ただし、作り直しではなく、調整の場合は6ヶ月以内でも可能です。
自由診療の場合

自由診療の場合の費用は、材料によって異なるため以下のように分類できます。
- マグネット義歯:66,000〜72,000円(税込)程度
- ノンクラスプデンチャー:110,000〜210,000円(税込)程度
- 金属床義歯:220,000〜528,000円(税込)程度(金属の種類による)
- シリコン義歯:100,000〜500,000円(税込)程度
- オーバーデンチャー:1,150,000〜2,150,000円(税込)程度
マグネット義歯は磁石を使用した義歯で、磁力を使って固定させます。
ノンクラスプデンチャーは、保険適用の義歯にある金属製のバネ(クラスプ)がなく、見た目が自然です。金属アレルギーの方にも適しています。
金属床義歯をチタン製にした場合は、プラスチック製の4分の1の薄さで作ることができるため装着の違和感が軽減できます。また、金属床義歯は食べ物の熱が伝わりやすいため、食事をよりおいしく食べることができるでしょう。
シリコン義歯は、歯茎に当たる部分がシリコンでできていて肌触りがよく、プラスチック製と比較すると違和感が少ない方法です。
咀嚼力の機能にもすぐれていて、食べられる食材の数が増える特徴があります。
オーバーデンチャーは、残存歯やインプラントを土台にして固定する入れ歯です。安定性が高く、噛む力が衰えにくいのが特徴です。
自由診療には複数の選択肢があります。見た目や快適さを重視したい方には向いているでしょう。
遊離端欠損への義歯以外の対処法

片側遊離端欠損の対処法は義歯だけではなく、ブリッジやインプラントを選択することも可能です。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、ここでは治療法の概要とともに詳しく解説します。
ブリッジ
一般的なブリッジは、欠損部の両側の歯を大きく削りその歯を支台歯とし、欠損部に人工歯をおく治療法です。ブリッジにより、咬合と咀嚼機能を回復させます。
簡単にいえば、両側の歯を削ってつなぐ方法なので、歯根膜に負担がかかる補綴(ほてつ)装置です。
ブリッジには特殊な形態のものがあります。遊離端に対して行うブリッジを遊離端ブリッジや延長ブリッジなどと呼びます。
通常のブリッジは奥に支える歯がなければ治療できませんが、遊離端ブリッジは奥の歯がなくてもできるのが特徴です。
遊離端ブリッジのメリットは以下のとおりです。
- 取り外さなくてよい
- 治療が短期間
- 保険適用内であれば費用を抑えることができる
- インプラントのような外科的処置が不要
義歯と比べると取り外さずに済むことが大きなメリットといえます。
一方、遊離端ブリッジのデメリットは次のとおりです。
- 通常のブリッジよりも支台歯の負担が大きい
- 場合によっては支台歯の寿命が短くなることがある
- 咀嚼力の回復ができない
遊離端ブリッジでは、支台歯の負担を軽減するために、欠損部に設置する人工歯(ダミーの歯)を小さくすることがあります。支台歯の負担が大きくなると歯根周辺の骨の吸収や歯根の破折を引き起こすことがあります。
インプラント

インプラント治療は、遊離端欠損の治療法として選択肢の一つになっています。特に入れ歯による遊離端欠損の治療に抵抗がある方には、高い満足度とQOLの向上が期待できる治療法です。
インプラント治療とは、顎の骨に人工歯根を埋め込み、その上に人工歯を装着する方法です。主なメリットは以下のとおりです。
- 天然歯に近い咀嚼力を得られる
- 自分の歯に近い感覚で違和感がなく食事が取れる
- 片側遊離端義歯とブリッジと比べるとより長持ちする方法である
- 隣の歯を削る必要がない
- 発音が安定して会話を楽しめる
- 取り外す面倒がない
- むし歯にならない
このように、インプラント治療による遊離端欠損への対処法はメリットが大きくなっています。一方、デメリットは次のとおりです。
- 人工歯根は感覚を持たないため、噛む力の感覚が鈍くなることがある
- 治療期間が長くかかる
- 外科処置に伴う痛みや腫れ・出血・合併症の恐れがある
- 保険適用外のため治療費が高額
- 適切なメンテナンスを怠ると、歯周病(インプラント周囲炎)を引き起こすリスクがある
インプラントを埋め込むためには、十分な骨の量が必要です。骨が不足している場合は、骨移植や骨造成が必要になることもあるため、治療を希望する際は歯科医師と十分に相談しましょう。
まとめ

奥歯を失って片側に支える歯がなくなった状態の欠損部分を補綴するために、片側遊離端義歯が使われることがあります。
遊離端欠損を放置すると、歯並びの乱れや噛み合わせの悪化に加え、むし歯や歯周病のリスクが高まります。
片側遊離端義歯は、フィット感や安定性に課題があるものの健康保険が適用され、ブリッジのように健康な歯を削らずに治療できます。
インプラント治療は、自分の歯にとても近い感覚でしっかり噛むことができるのがメリットです。
ただし、インプラント治療は自費診療のため、治療費が高額になったり治療の期間が長くかかったりする側面があります。
ブリッジは、インプラントのように取り外しの手間がない点がメリットですが、咀嚼力に難点があります。
このように、片側遊離端義歯のメリットやデメリットと、その他の対処法があることもわかりました。
どの対処法を選択するかは、一人ひとりのライフスタイルや予算に合わせて検討することが大切です。
参考文献
