更年期には女性ホルモンの変化によりさまざまな身体症状が現れますが、そのなかでもドライマウス(口腔乾燥症)は見過ごされがちな症状の一つです。お口の乾燥は単なる不快感だけでなく、口内の健康状態や全身の健康にも影響を与える可能性があります。この記事では、更年期とドライマウスの関係、ドライマウスの症状や治療法、そして日常でできるセルフケア方法について解説します。
更年期とは

更年期は女性の生殖機能が終了に向かう重要な移行期間であり、多くの女性が身体的・精神的な変化を経験する時期です。更年期の期間中に起こるホルモンバランスの変化は、さまざまな症状を引き起こします。
更年期が始まる時期
更年期とは、閉経を挟んだ前後約10年間の時期を指し、一般的には45~55歳頃にあたります。日本人女性の平均閉経年齢は約50.5歳とされており、個人差はあるものの、多くの方が50歳前後で閉経を迎えます。
更年期は、以下のような段階に分けられます。
- 閉経移行期(閉経前期):閉経のおよそ7年前から月経周期に変化が現れ始める時期
- 閉経後早期:閉経後5~8年のうち、特に最初の2年間は更年期症状が現れやすい
- 閉経後後期:閉経から8年以上が経過した時期
更年期に身体で起きること
更年期には、卵巣機能の低下に伴い、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少します。女性ホルモンの変化により、心身にさまざまな不調が現れるようになります。
主な更年期症状には、以下のようなものがあります。
【血管運動神経症状】
- のぼせ、ほてり、発汗(ホットフラッシュ)
- 動悸、息切れ
- めまい
【精神的症状】
- イライラや不安感
- 抑うつ気分
- 不眠
【身体的症状】
- 肩こりや腰痛
- 疲労感、倦怠感
- 頭痛
また、エストロゲンには皮膚や粘膜を保護し、潤いを保つ働きがあるため、エストロゲンの分泌量が減少すると、口内の乾燥が起こりやすくなるのも特徴です。
ドライマウスとは

ドライマウス(口腔乾燥症)とは、さまざまな原因によって唾液の分泌量が減少し、口内が乾燥する状態を指します。ここでは、ドライマウスの症状、ドライマウスが口内に与える影響、ドライマウスの症状を発症する病気について解説します。
ドライマウスの症状
ドライマウスで起きやすい自覚症状をご紹介します。
- お口の中が乾く、ネバつく
- 水を頻繁に飲みたくなる
- 夜中にお口の渇きで目が覚める
- パンやビスケットなど乾いた食べ物が食べにくい、飲み込みにくい
- 味が変わったように感じる(味覚異常)
- 話しにくい、滑舌が悪くなる
- 舌がヒリヒリ、ピリピリと痛む
- 口臭が気になるようになる
ドライマウスが口内に与える影響
唾液は、口内でとても重要な役割を担っています。まず、洗浄、自浄作用により食べかすや細菌を洗い流し、口内を清潔に保ちます。また、唾液に含まれる抗菌成分や免疫物質は、有害な細菌の増殖を抑え、口内の感染症から身体を守っています。
さらに、唾液は消化にも関与しており、でんぷんなどの栄養素の分解を助けることで、消化吸収を促進します。加えて、初期のむし歯を修復する再石灰化作用も重要です。唾液中のカルシウムやリン酸が歯に作用し、初期むし歯の進行を防ぎます。また、粘膜の保護作用により、口内の軟組織を乾燥や外部刺激から守る働きもあります。
しかし、ドライマウス(口腔乾燥症)によって唾液が不足すると、こうした機能が大きく低下し、さまざまな問題が生じます。
口内への影響は、主に以下があります。
- むし歯や歯周病のリスク増加
自浄作用と抗菌作用の低下により、細菌が増殖しやすくなります - 口臭の悪化
細菌の代謝により、揮発性硫黄化合物などの臭気成分が増えるためです - 口内炎ができやすくなる
粘膜が乾燥し、傷つきやすくなることで炎症を起こしやすくなります - 舌痛症の出現
見た目に異常がないのに、舌がピリピリ・ヒリヒリと痛むのが特徴です。舌の先や側面に痛みを感じやすく、口の乾燥やしびれをともなうこともあります - 味覚障害
唾液の不足により、味蕾への刺激伝達が妨げられ、味がわかりにくくなります - 口腔カンジダ症の発症
抗真菌作用が低下し、カンジダ菌が異常に増殖することで起こります
全身への影響は、主に以下があります。
- 摂食嚥下障害
唾液が少ないと食べ物をまとめにくく、嚥下反射も起こりにくくなります - 誤嚥性肺炎のリスク増加
嚥下障害を介した場合、飲食物や唾液が誤って気道に入り、肺炎を引き起こす可能性が高まります - 感染症にかかりやすくなる
口内の免疫機能が低下することで、風邪などの感染症にもかかりやすくなります
このように、ドライマウスは単なるお口の乾燥にとどまらず、口腔の健康から全身の健康にまで影響を及ぼす可能性があるため、早期の対応と適切なケアが重要です。
ドライマウスの症状が出る病気
ドライマウスは、さまざまな原因によって引き起こされます。疾患ではシェーグレン症候群(自己免疫疾患)、糖尿病、腎不全、更年期障害などが挙げられます。これらは唾液腺の機能に直接的または間接的な影響を及ぼします。薬剤の影響も大きく、特に抗うつ薬、抗不安薬、降圧薬、利尿薬、抗ヒスタミン薬、抗パーキンソン薬などの服用が唾液の分泌を抑制することがあります。そのほかの要因は、ストレスや緊張、口呼吸、加齢に伴う唾液腺機能の低下、放射線治療の副作用などが関係します。
このようにドライマウスは、疾患や薬剤、生活習慣など複数の要因が重なって発症することが多いため、原因の特定と適切な対処が重要です。
更年期にドライマウスになりやすい理由

更年期にドライマウスが生じやすくなる背景には、主に女性ホルモン(エストロゲン)の分泌低下と自律神経の乱れが関係しています。
エストロゲンには、皮膚や粘膜の保護作用や潤いを保つ働きがあり、皮膚の含水量を高めたり、コラーゲンやヒアルロン酸の合成を促進したりする効果が知られています。そのため、更年期に入って加齢とともにエストロゲンの分泌が減少すると、皮膚や粘膜の乾燥が進み、バリア機能も低下します。これにより、かゆみやチクチクとした不快感が生じるほか、唾液の分泌も調整が乱れやすくなり、ドライマウスを引き起こしやすくなります。
さらに、更年期は脳の視床下部にも影響を及ぼし、自律神経のバランスが崩れやすくなります。自律神経の乱れにより、のぼせや発汗、イライラ、不安感などの更年期症状が現れ、その一環としてドライマウスが生じることもあります。
また、更年期障害による不定愁訴に悩むなかで、抗うつ薬などを服用する方もいますが、抗うつ薬などの副作用として唾液分泌の低下(薬剤性ドライマウス)が起こることがあります。唾液が出にくくなること自体がさらにストレスとなり、ドライマウスの症状が悪化する悪循環に陥るケースも報告されています。
このように、更年期のホルモン変化と自律神経の不調、そして心理的・薬理的要因が複合的に関与して、ドライマウスが引き起こされやすくなります。
更年期のドライマウスは放置しても大丈夫?

更年期に見られるドライマウスは、放置しないことが大切です。唾液の分泌が低下した状態をそのままにしておくと、口内だけでなく全身にもさまざまな悪影響が及ぶ可能性があります。
口内への主な影響
唾液による自浄作用が低下し、口臭が強くなりやすくなります。また、舌がヒリヒリと痛む舌痛症を併発すると、食事や会話に支障をきたすこともあります。さらに、唾液の抗菌作用が弱まることで、むし歯や歯周病の原因となる細菌が増殖しやすくなります。
全身への影響
唾液不足により摂食や嚥下が難しくなる摂食嚥下障害が生じると、食事が取りづらくなるだけでなく、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。また、口内の免疫機能が低下し、風邪などの感染症にもかかりやすくなります。
摂食嚥下障害に関連して現れる症状には、舌痛症、味覚障害、強い口臭、粘膜疾患、むし歯、歯周病などがあり、症状の程度や背景に応じた適切な対処が必要です。
背景疾患への注意も必要
ドライマウスの背後には、シェーグレン症候群などの自己免疫疾患が隠れていることもあります。症状がつらい場合や長引く場合には、早めに医療機関を受診し、原因の特定と適切な治療を受けることが大切です。
更年期のドライマウスの治療法

近年では、ドライマウスを専門的に診療する外来も設けられており、症状の背景を踏まえた総合的な治療が行われています。
受診を検討すべきタイミング
お口の乾燥が長く続いている、日常生活に支障が出るほど症状がつらい、セルフケアを試しても改善しないなどの場合は、医療機関の受診を検討しましょう。
また、食事や会話がしにくい、舌に痛みやひび割れがある、口内炎を何度も繰り返すなどの症状がある場合も、早めに医療機関を受診することをおすすめします。
ドライマウスの診療科
まず、口腔外科では口腔乾燥外来やドライマウス外来が設けられていることが多く、専門的な検査や治療を受けることができます。
また、内科では糖尿病などの持病が原因となっている場合の診断や管理、自己免疫疾患のシェーグレン症候群の確認などが行われます。
さらに、婦人科では更年期障害に対する全体的なケアや、ホルモン補充療法が必要かどうかの判断なども行っています。
ドライマウスの原因によって、受診すべき診療科が異なることがあるため、気になる症状がある場合は、まず専門医に相談してみましょう。
ドライマウスの治療法
まずは、生活習慣や服用している薬の見直しが大切になりますが、症状がつらい場合には、お口の乾燥をやわらげるお薬や漢方薬(白虎加人参湯)が使われることもあります。
お薬は、唾液の出を助ける飲み薬があり、特に自己免疫の病気が関係している場合には、保険で処方されることもあります。症状が続くときは相談が大切です。
更年期のドライマウスへのセルフケア

ドライマウスの症状をやわらげるために、日常生活で取り入れられるセルフケアがあります。これらの方法は、医師のアドバイスを受けながら無理のない範囲で続けることが大切です。セルフケアを行っても症状が改善しない場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
唾液腺マッサージをする
唾液腺マッサージは、唾液の分泌を促し、お口の中の乾燥をやわらげるのに効果があります。
唾液をつくる場所はいくつかあり、主に耳の前にある耳下腺、顎の下にある顎下腺、舌の下にある舌下腺があります。マッサージでは、これらの部分をやさしく刺激します。
まず、耳の前に指をあて、円を描くように軽く押します。次に、顎の下に親指をあて、舌を下から押し上げるようなイメージで、左右同時にゆっくりと押します。強く押しすぎず、心地よいと感じるくらいの力加減が目安です。しばらくマッサージを続けると、ジワーッと唾液が出てくる感覚が得られることがあります。
毎日少しずつ続けることで、お口の中のうるおいを保つ助けになります。
鼻呼吸を心がける
歯並びや癖、鼻づまりなどでお口が閉じにくいと、無意識のうちに口呼吸になってしまうことがあります。すでに口呼吸が習慣になっている場合も、日常生活のなかでお口を閉じ、鼻で呼吸をすることを意識するだけでも、症状の改善につながります。
咀嚼回数を増やす
ものをかむことで、顎の筋肉が刺激され、唾液腺の働きが活発になります。しかし近年は、食生活の変化により、かむ回数が少なくなってきており、噛む回数がドライマウスの一因とも考えられています。食事の際は、よくかむことを意識し、やわらかいものばかりでなく、適度にかみごたえのある食材を取り入れるようにしましょう。また、キシリトール入りのガムをかんだり、梅干し、レモン、お酢などの酸味のある食品や、納豆、昆布、するめなど唾液を促す食べ物を意識してとるのも効果的です。
ストレス管理を心がける
ストレスや緊張は、唾液の分泌を抑える原因になります。
特に更年期は心身のバランスが崩れやすく、ストレスがたまりやすい時期です。そのため、日頃から無理のない範囲でストレスを和らげる工夫が大切です。リラックスする時間を意識的にとりましょう。ヨガや深呼吸、瞑想などは、副交感神経を整え、お口の中のうるおいを保ちやすくします。軽い運動も気分の安定につながり、心と身体の両面によい影響があります。
また、規則正しい睡眠、趣味の時間、お風呂やアロマなどで心地よく過ごすことも効果的です。さらに、こまめな水分補給を心がけ、飲酒や喫煙はできるだけ控えましょう。これらの習慣が、ドライマウスの予防や症状の軽減につながります。
まとめ
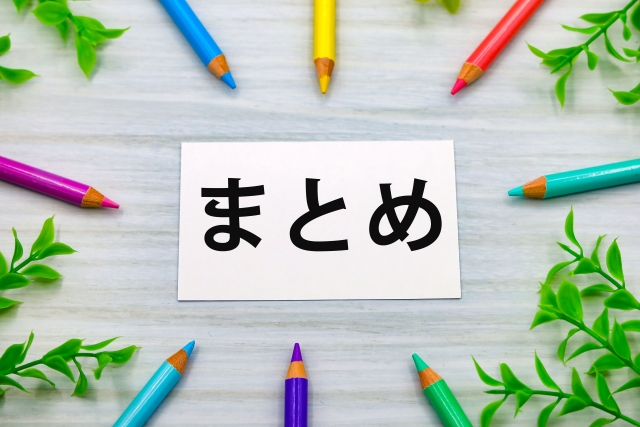
ドライマウスは、更年期にみられる重要な症状のひとつです。エストロゲンの減少や自律神経の乱れによって唾液の分泌が減り、お口の中が乾きやすくなります。
この状態を放っておくと、むし歯や歯周病、口臭、摂食嚥下障害などのトラブルを引き起こす可能性があります。さらに、誤嚥性肺炎など、深刻な合併症につながることもあるため、早めの対応が大切です。
特に更年期のドライマウスは、きちんと対処すれば改善が期待できる症状です。気になることがあれば我慢せず、早めに専門の医師に相談し、自分に合った治療やセルフケアを取り入れて、快適な日常を目指しましょう。
参考文献
- https://www.ginza-somfs.com/xerostomia.html
- https://www.lotte.co.jp/kamukoto/mouth/541/
- https://www.osaka-dent.ac.jp/hospital/drymouth.html
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/jshowaunivsoc/77/4/77_367/_pdf/-char/ja
- https://drymouth-society.jp/
- https://www.jda.or.jp/park/trouble/index10.html
- https://wakamoto-pharm.co.jp/wakanote/oral-care/dry-mouth/
